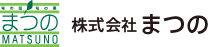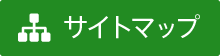こんにちは。
福井県のまつのべジフルサポーター
野菜ソムリエプロ
だしソムリエ協会認定講師の
水嶋昭代です。
今回は、福井を飛び出し、静岡県焼津市へかつお節工場の見学に行ってきました。
だしだけではなく、料理にかけたり、和えたりと毎日の食生活には欠かせないかつお節。かつお節には、カビ付けしていない「荒節」とカビ付けした「枯れ節」があります。まずは、その製法についてお話いたします。
主な産地は、鹿児島県の枕崎、指宿、静岡県の焼津です。原料のカツオは、日本の近海でも獲れますが、脂肪は酸化しやすく劣化が早い、だしがにごりやすいなどの理由から、現在は、脂肪分の少ない南洋のカツオが多く使われています。主にインドネシアやパプアニューギニアのあたり、赤道近くの海で、巻網などの方法で漁獲されます。遠洋で獲れたカツオは、船内において、ブライン凍結法(飽和食塩水をー25度の凝固点ぎりぎりまで冷やして、その中に魚を漬け込んで凍結する)で急速冷凍され、鮮度を保ったまま日本に運ばれます。
【生切り】熟練した職人さんの手により、主に5kg近いカツオをおろしていきます。


3キロ未満の小さなカツオは、半身のまま加工され、形が亀の甲羅に似ていることから「亀節」と呼ばれます。
【籠立て(かごたて)】カツオを身を崩さないように丁寧に籠に並べます。綺麗なかつお節を作るために大事な作業です。
【煮熟(しゃじゅく)】85度~96度で約2時間茹でます。茹でた状態のものが、「なまり節」です。また、この煮汁が一部の顆粒だしなどに使われます。



「一番火」(水抜き焙乾)と呼ばれる最初の焙乾は、表面の雑菌を殺すために85度~90度で1時間行われます。
二番火以降の【間歇焙乾(かんけつばいかん)】は、「焙乾」と冷まして寝かせる「安蒸」を10回ほど繰り返します。焙乾終了後の水分量は、元のカツオの23%ほどです。ここまでの工程で完成したものが「荒節」です。約1か月で完成します。こちらが主に関西で好まれる「花かつお」になります。
【カビ付け】形が良く、質の良いものだけに、かつお節優良カビを噴霧します。
☆(株)にんべん様が分離・研究し、日本鰹節協会様に供給しているユーロティウム属のかつお節優良カビが全国のかつお節の生産に使われています。
カビ付けをする意味は、
①カツオ節の水分を更に抜き、保存性を高める。
②魚臭さが減り、かつお節特有の香りが付く。
③分解酵素により、更にうま味が発生する。
④他の菌の繁殖を防ぐ。
⑤だしの濁りがなくなる。

今回、株式会社にんべん様の提携企業、株式会社丸栄様と株式会社山七様、そして(株)にんべん大井川工場様の見学をいたしました。にんべん様の工場では、削り立てをすぐに袋詰めし、フレッシュな削り節を供給されています。
今回は、かつお節が出来るまでの工程を中心にレポートしました。引き続き【後編】は、かつお節の違い、だしのひき方とかつお節を使った料理についてお届けします。
福井県のまつのべジフルサポーター
野菜ソムリエプロ
だしソムリエ協会認定講師
水嶋昭代でした。